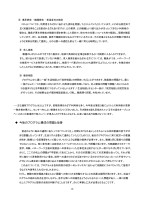就労移行支援事業所 チャレジョブセンター熊谷 2015年度事業報告書
11/14
10 ⑧ 業界研究 ・職種研究 ・希望条件の検討 これらについては、利用者それぞれにあわせた資料を用意してとりくんでいただいています。いわゆる就活本で 広く知識を得ることを選ばれる方もありますが、どの業界、どの職種という絞り込みがまったくできない利用者の 場合は、職員が厚生労働省の職業分類を参考にした資料で、世の中の仕事について大枠で解説し、理解を確認 しています。また、ある程度、業界や職種の絞り込みができている方には、その対象となるものの理解が深まるような資料を用意して提供し、その分野への適性も併せて一緒に考える時間としています。 ⑨ 求人検索 職種のしぼりこみができてきた場合は、地域や具体的な企業を検索するという段階に入ることができます。 また、絞り込みまで到達していない時期に、求人検索を組み込まれる方については、職員がつき、ハローワークの検索サービスを利用する方法を紹介し、検索ワード選びかたのコツも説明するようにしています。作業自体をしたことがない利用者もいるため、何回か行うようにしています。 ⑩ 個別相談 プログラム中に週に一度「生活相談」か「就労相談」の時間をいれることができます。職員数の問題から、週に 一度どちらか一つの相談にはなりますが、利用者は随時利用しており、対人関係の問題や課題へのとりくみの 行き詰まりなどを早期発見につながっているといえます。「生活相談」はセンター長が、「就労相談」は就労担当 が行っており、その結果は必ず個別相談記録として残し、職員間で回覧、共有されています。 ・・・主な通所プログラムは以上ですが、資格取得をめざす利用者も多く、今年度は簿記3級にとりくんだ利用者が見事一発合格を果たし、センター内によい刺激を与えてくださいました。引き続き2級も目指されているその姿をオープンスペースのこの事業所で他メンバーが見ることができることなども、お互い高めあう効果となっています。 ◆ 今後のプログラム構成の問題と改善 前述のように毎日の通所にあたっては「マンネリ化」、仲間との「なれあい」とそれらによる目的意識の低下が大きな課題となっています。生活リズムを整えて通所していただくためには、毎日のプログラムに常に就労への意識を抱き、職場にいる緊張感をもって臨んでいただくような課題の提供が必要です。また、職場と同じ環境での課題ではないことから、特に若年者には就労のイメージがつかみにくいという問題があります。外部講師のセミナーや見学、体験、ハローワーク主催の面接会への参加といった仕事社会と接することが一助になればと考えています。さらに、ここでの机上の課題が「学習的」であることから、その日の課題に対しての充実感はあっても、それが就労に結びつく資格取得でない場合、就労への道のりのどの辺まできているのかがわからないといった不安やいつ、どうなったら具体的に職種の絞り込みや就職活動にはいるべきなのかがわからないという声もでています。 この点については、プログラムを各利用者の就労へのレディネスに合わせて段階的にカテゴライズして提供するなども今後考えられるかもしれません。 ただし、実際の就労場面と重ならない課題への取りくみを段階化することの効果は疑問が残ります。また、自由プログラムが組める利点を活かしながら、苦手分野への消極性をどうとらえるかといった問題があり、一律に段階 化したプログラム提供の良否を判断することはできず、さらに考察と工夫が必要となるところです。
元のページ